 栄養ミニ知識
栄養ミニ知識 ニンニク (ガーリック)
我が国では餃子の具や焼肉のタレとして多用されています。食欲をそそる香味のほか、肉の臭みを消す目的にも用いられます。ニンニクにはビタミンB1、B2が豊富に含まれ、摂取するとアリシンがビタミンB1にくっついてアリチアミン(市販品アリナミン)にな...

 栄養ミニ知識
栄養ミニ知識  栄養ミニ知識
栄養ミニ知識  健康ミニ知識
健康ミニ知識  免疫のはなし
免疫のはなし  環境問題
環境問題  健康ミニ知識
健康ミニ知識  環境問題
環境問題 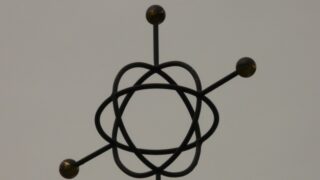 核医学のはなし
核医学のはなし 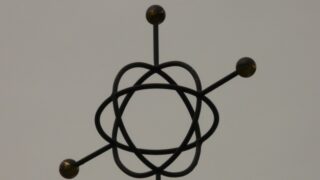 健康ミニ知識
健康ミニ知識  健康ミニ知識
健康ミニ知識  栄養ミニ知識
栄養ミニ知識  感染症
感染症  健康ミニ知識
健康ミニ知識  栄養ミニ知識
栄養ミニ知識  栄養ミニ知識
栄養ミニ知識  健康ミニ知識
健康ミニ知識  健康ミニ知識
健康ミニ知識  健康ミニ知識
健康ミニ知識  栄養ミニ知識
栄養ミニ知識  栄養ミニ知識
栄養ミニ知識  栄養ミニ知識
栄養ミニ知識  栄養ミニ知識
栄養ミニ知識 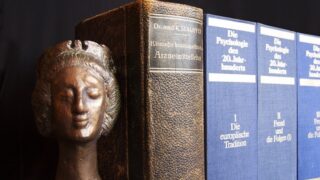 心理学のはなし
心理学のはなし  再生医療
再生医療  栄養ミニ知識
栄養ミニ知識